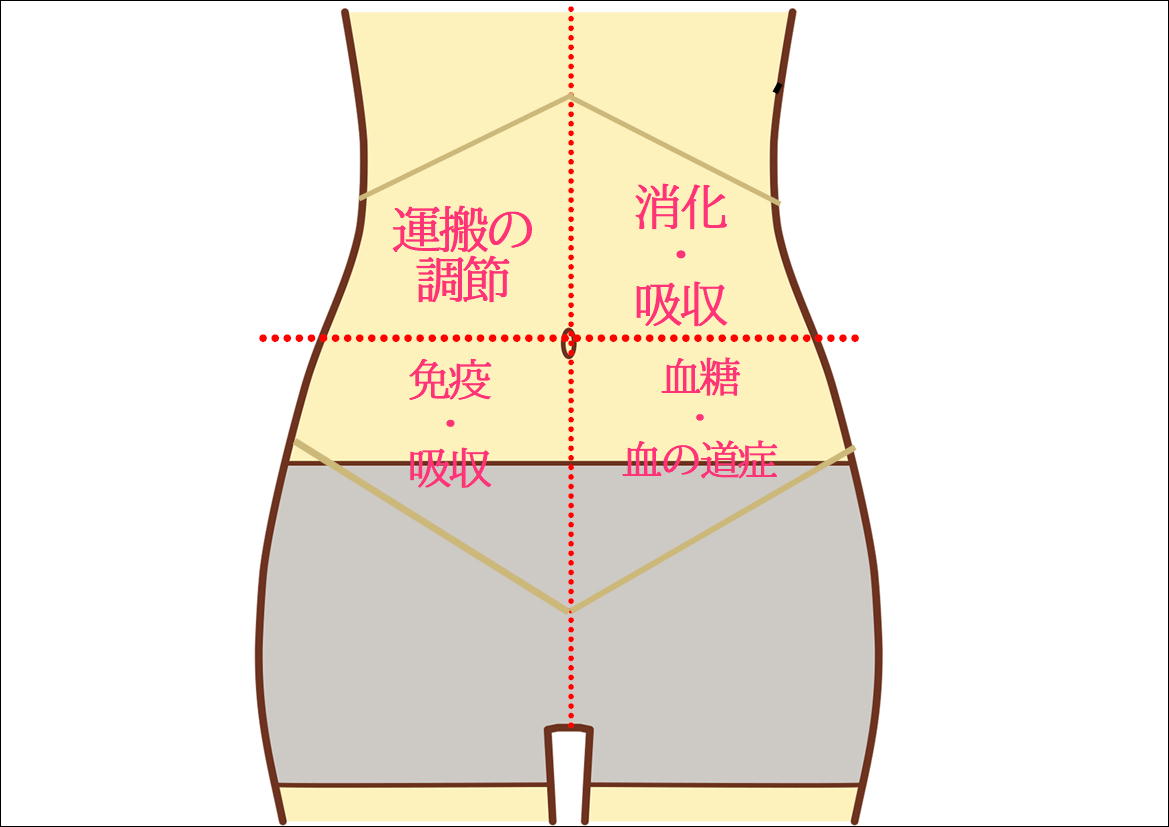
前回に引き続きのお話になります。
上記の内容は、東洋医学と西洋医学基礎・理論の考えを組み合わせた
私の考える腹診であります。
私の考えであるため、見る方には当てはまらないこともありますが
こんな考えもあるのかと見て頂ければ幸いです。
長くなるためパート4に分けてお話をします。
①運搬の調節
右側の季肋部には「肝臓」があります。
| 西洋医学の働き | 東洋医学の働き |
|---|---|
| 代謝と解毒 | 気の流通調節 |
| 胆汁の生成 | 血の貯蔵 |
| 血液の貯蔵 |
筋の運動機能調節 |
| 栄養素の貯蔵 | 精神活動の安定 |
肝臓は横隔膜と腹壁から伸びる膜(肝鎌状間膜)によって支えられています。
肝臓の機能が低下することで、肝臓の動きが悪くなり臓器を支えている横隔膜の
働きも悪くなることが考えられます。
さらに横隔膜は肋骨・胸骨・腰椎に付着し、呼吸運動に合わせて連動しています。
呼吸運動の低下(呼吸が浅くなる)による腹式呼吸を行うことが難しくなります。
それに伴い、横隔膜は硬くなり季肋部が硬くなる状況が発生すると考えます。
これが東洋医学の腹診で診る「胸脇苦満(きょうきょうくまん)」所見の原因に
繋がっているのでは、ないかと私は思います。
肝臓は脂肪の消化・吸収に重要な役割を果たす「胆汁」を、生成しています。
胆汁が脂肪の分解産物に作用して、小腸から吸収しやすい状態を作っています。
そのため脂質の消化・吸収には必要不可欠の働きをします。
さらに肝臓は糖類・たんぱく質・脂質をはじめとする栄養素を
分解・合成・貯蔵の働きを行います。
消化・吸収された後の人体の化学工場となり、
肝臓は体の活動を円滑に支える臓器とも言えます。
東洋医学では「肝は疏泄を主る」とされています。
疏泄…①隅々までゆきわたる②円滑でよどみのない
意味を持ちます。
「肝」には気や血の流れを円滑に、かつのびやかにする働きがあります。
「イライラして胃が痛くなった」・「ストレスで食欲がない」など
肝の働きがのびのびしていることで、気も順調に巡り、精神も安定し、
胆汁の分泌もよく、胃腸の消化を助ける。
しかし肝の働きが悪くなると、気が滞り、精神不安(抑うつ傾向)、イライラしたり怒りっぽいなどの症状を発症し、胃腸の障害となります。
肝の働きは、各臓器がうまく働くように調子を整えていると言えます。
直接的ではなく間接的にバランスを整え、臓器が生き生きと正常に働くことを支えています。
そのため、右季肋部周辺の反応を診ることで
人間関係・環境の変化によるストレスが体の負担となり
「肝」の働きを悪くさせていると判断できる。
それが治療方針の選択となります。
ツボとしては
右不容(ふよう)・右期門(きもん)・右承満(しょうまん)
・右章門(しょうもん)・右季肋部周辺