
「腹診」と「腹治」
「お腹を診て病気の状態を知る」
お腹を診ることを「腹診」「診腹」「按腹」などと呼びます。
腹診は中国ではあまり重要視されず
日本独自で発達をとげ、主に湯液(日本漢方)の診断として用いられる。
漢方理論の原則である、「虚・実」
●腹力が強いのか弱いのか
●押して抵抗の有無
●押して圧痛の有無
●腹壁が緊張しているのか、ふにゃふにゃしているか
●触ってくすぐったいのか無いのか
●拍動の有無
●皮膚がザラザラしているのか、べちょっとしているか
挙げればまだまだありますが
患者さんのお腹の所見を診ていきます。
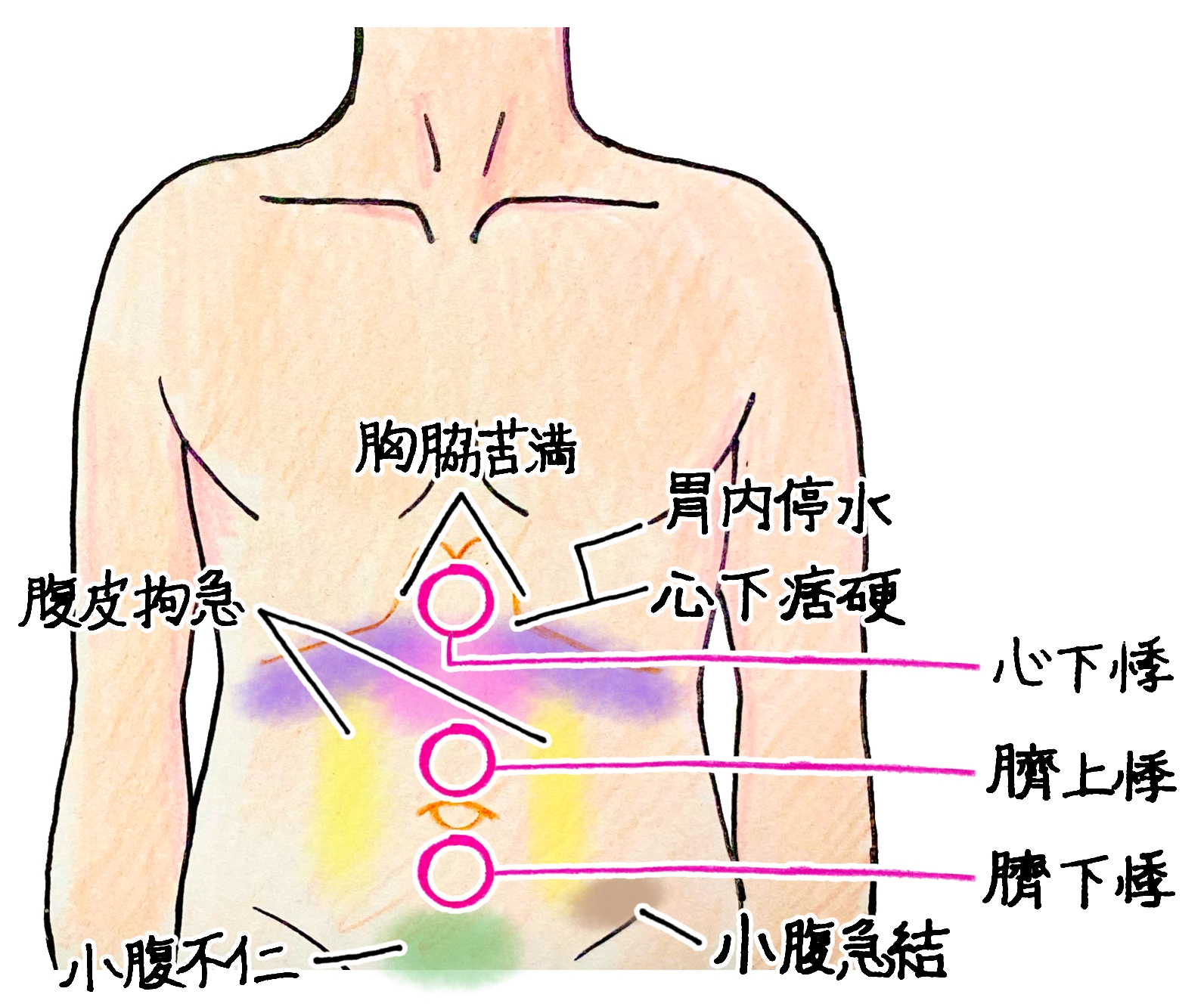
上記の所見に従い、治療法が決まります。
例えば胸脇苦満
胸脇苦満(きょうきょうくまん)
両側の季肋部と脇腹、側胸部を含む範囲に出現するものがあります。
同部位に鈍痛や圧迫感を伴い、抵抗痛を生じる。
↓
ストレスを感じ体が緊張して、呼吸が浅くなっている状態
胃腸機能も低下している。
↓
自ずと経穴(ツボ)が決まる。
診断即治療
「目に見ぬことはいわず」
江戸時代 医師 吉益東洞先生の言葉であります。
患者さんに、「気の流れが悪い」「熱がこもっている」
「気が滞っている」などの言葉を言っても伝わらない。
お腹のこの場所が悪いから、体の状態がこうなっていると説明をします。
さらに、西洋医学の知識を含めて説明すると更に
分かりやすく養生の仕方までお話ができる
すばらしい診断方法であります。
すばらしい診断方法ですが
腹診だけに頼り過ぎても、病を見落とす可能性があるため
全身を観察し、さらに腹診をして、状態を細かく分けていく
どんな考えでも良い所と足らない所があります。
しかし、色々な方法を取り入れると本来の病を
見失い結果、患者さんの体は変わらない気がします。
基礎基本に忠実に、良い所を取り入れ
自分の治療方針を定めていく
守・破・離
次回お話したいのは
西洋医学と日本漢方の良いところを組み合わせた
私独自の考えであります。
しかし、この考えに至るのも
基礎があって日々の臨床から経験し
経験を積み重ね少しずつ分かってきた事であります。